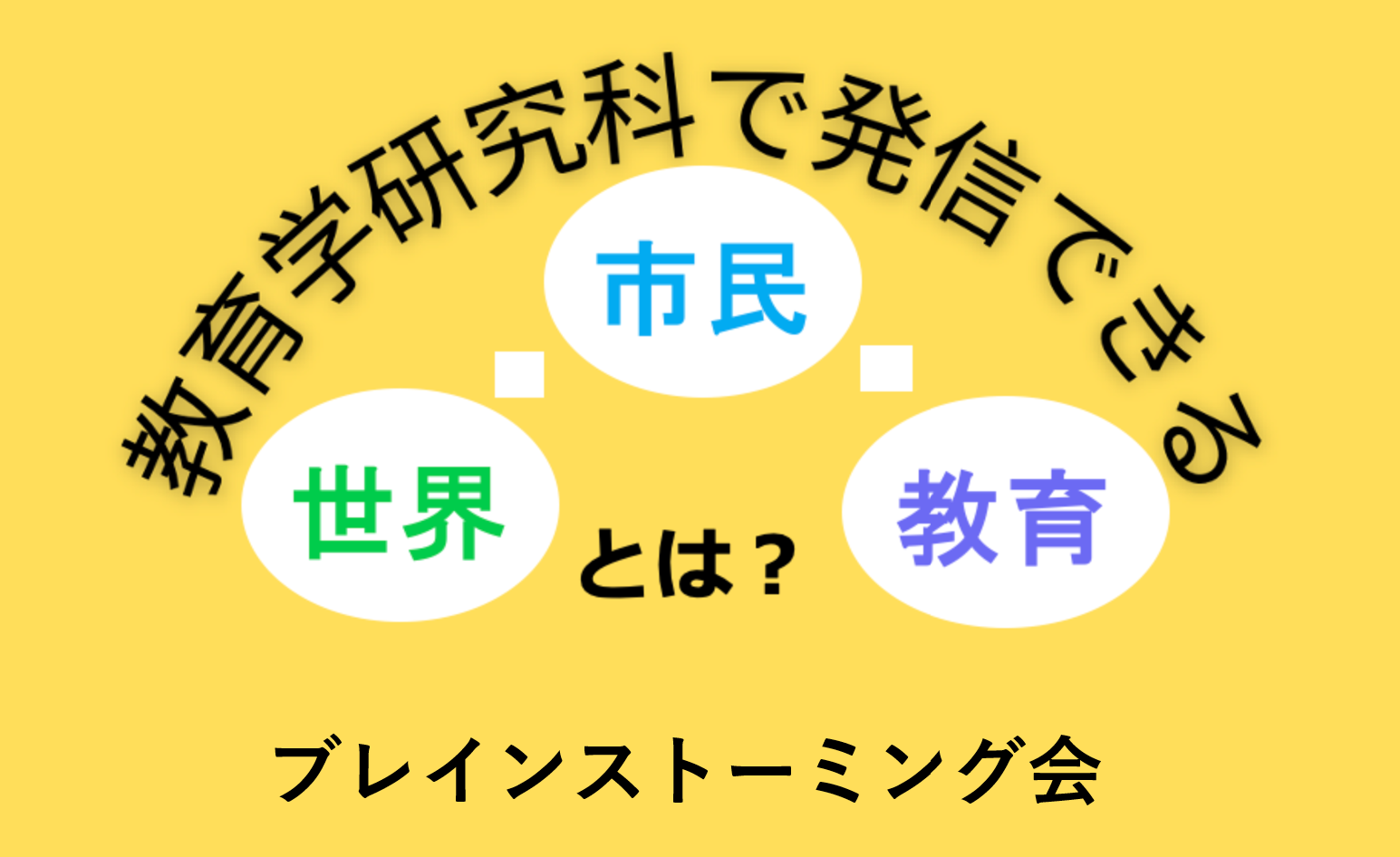2025年3月27日(木)、多文化教育チームのPark Joon ha 先生、Thomas Brotherhood先生、田野茜さん、奥村好美の四人が名古屋国際学園(Nagoya International School, 以下NIS)を訪問しました。名古屋国際学園は、1964年創立のインターナショナルスクールで、多様な文化的背景を有する子どもたちが通っています。現在は、IBプログラムの認定校でもあります。訪問時は、学園長Matthew Parr先生および小学校長Travis Peterson先生それぞれへのインタビュー、学校の案内、授業観察の機会をいただきました。
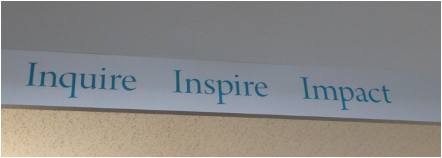
NISでは、「Inspire, Inquire, Impact」および「Inclusiveness」が学校の理念として大切にされています。授業は英語で行われますが、子どもたちの第一言語は多様であり、学校で英語以外の言語を使うことも認められています。ただし、NISではどのような行動を取るかが重視されており、英語以外の言語を使う際には、それによりその言語が分からない誰かを排除してはいけないことがルールとされています。実際に、校内を歩いていると、日本語など英語以外の言葉も聞こえてきました。また、校舎の中心にある図書館には、様々な言語の本が並べられていたり、お手洗いの表示に複数の言語が使われていたりする様子も見られました。訪問日の翌週には、国際週間(International week)が予定されており、子どもたちがそれぞれの国の伝統的な服を着るなどして、それぞれの文化について楽しく学べるような活動が行われるとのことでした。
教科の授業でも、IBプログラムに基づき、探究的な学習が重視されています。訪問時には、MYP(Middle Years Programme)の国語の授業の一部を見せていただきました。ちょうどシェイクスピアの戯曲についての単元が終了したところで、生徒たちは各自のデバイスに振り返りを記入していました。その際、①読んだ戯曲についての理解、②その戯曲についての理解に役立ったクラス活動、③必ずしも役立たなかったクラス活動の三つについて生徒は記入を行っていました。概念理解を重視して授業が進められてきたことがうかがえます。また、生徒たちの振り返りは、教師にとっても単元での取り組みの振り返りにつながるように思われます。振り返りの記入後は、シェイクスピアの単元を通じて育まれたスキル等についてクラス全体で交流が行われた上で、新しい単元の導入がなされました。続く新しい単元では、Art Spiegelmanによる『マウス(MAUS)』が扱われます。最初に、生徒たちは表紙からどのような話かを想像して各自のデバイスに入力していました。その際、生徒には一人一冊『マウス』が配られていました。入力後は、生徒たちは想像したことをクラス全体で交流し、Art Spiegelmanが『マウス』を執筆するに至った経緯について語るインタビューの動画を見て、本の背景理解を深めていました。
授業では、生徒たちが自分の考えを持ち、探究的に読んでいくこと、その結果としてどのように理解が深まったかが自覚できるようになることが重視されているように感じられました。IBプログラムは必ずしも多文化教育を意図したプログラムではないかもしれませんが、生徒が探究的に学ぶとともにそれを交流する機会を保障することで、一人ひとりの学習者が自分らしく学ぶこと、互いに学び合うことを重視しているように思われました。このことは多文化教育にとっても重要なことであると考えられます。NISで学ばせていただいた視点は、インターナショナルスクールに限らず、日本の多くの学校においても、多様な子どもたちを包摂する上で大切な視点となるように思われます。貴重な訪問の機会をくださったNISの先生方、皆様にこの場をお借りして御礼申し上げます。
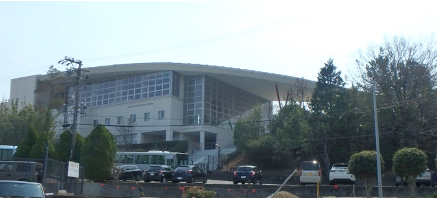
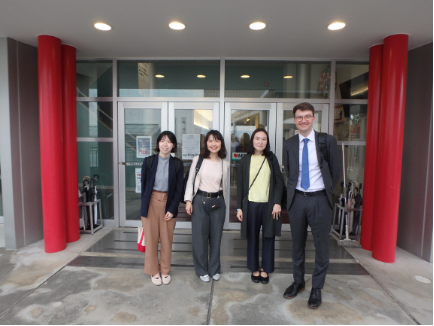
文責:奥村好美